したたかな京都の町、重層的な人間関係の中で(前編)

小山田徹|京都在住歴 45年
小山田さんの人生を語る上で、ダムタイプの活動、京都市立芸術大学での時間を外すことはできません。国際的にも注目されたその活動を小山田さんの視点から紐解きます。そして、その活動を織りなした日々の小さなできごとや、支えてくれた人たちの存在、京都の町でどのような交流があったのか、ハレとケのケのエピソードもお届けします。
取材場所は、京都市立芸術大学学長室
取材:2025年6月
2人きりの美術部
私は鹿児島出身で、通っていた中学校はものすごく田舎の、古い木造校舎。そこで美術にのめり込んでいきました。何があったかというと、中学生のときって妙なことを始めたりするじゃないですか。当時は「朝早くに学校へ行って、敷地のどこかを掃除する」というのが自分の中で流行っていました。そんなある日、学校の端っこの方、美術室のすぐ裏手の林を1人で掃除していると、そこからコーヒーのめっちゃいい匂いがするんです。ふっと覗くと、イタリアから帰国して着任された27歳くらいの若い女性の先生がコーヒーを淹れていて。目が合って「(コーヒー)飲む?」って誘われたんです。もう、そりゃあ、舞い上がります(笑)そうして教官室でいろいろ話している中で「美術に興味があるんやったら、放課後に来てくれたらいろんなこと教えられるよ」と言われ、2人だけの美術部のようなものが始まりました。放課後に、版画をやったり、絵を描いてみたり、いろいろやらせてもらいました。
先生の教官室にはいろんな骨董品や古い本が並んでいて、背伸びをしながら全部借りて読みました。全ての美術の知識は中学生の時に入った感じかな。パウル・クレーなどの造形思考なども全部ノートに写しました。少年としてちょっとエロスを感じながら(笑)これが美術への入り口です。
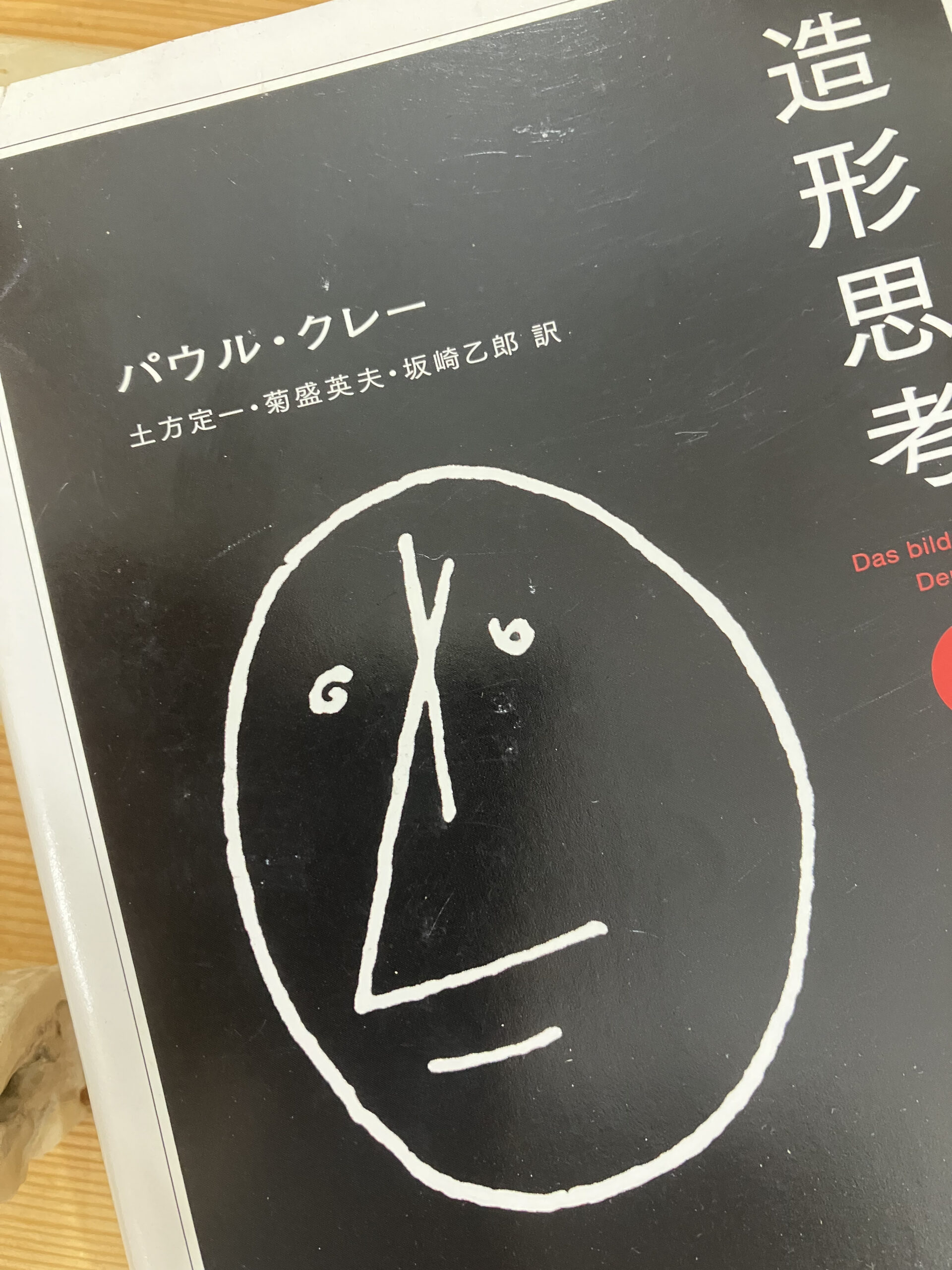
県下の高校生が集まってつくった私塾
それから急激に、中二病がこじれたように美術に向かっていきました。おかげで、高校受験に失敗し、1年間だけ中学浪人しました。その間だけちょっと勉強をがんばって進学校に入学したものの、その時から美術の道に進むことは決めていたので、ドロップアウト組としてずっと美術室に通う特別待遇の生徒でした(笑)そこで出会ったのが、今でも美術作家として活躍されている藤浩志さん。私が1年生で、藤さんが3年生でした。藤さんも美術の大学に進もうとされていて、2人仲良く美術談議を繰り広げていました。美術の勉強をしているように見せかけて、いろいろな遊びをずっと開発していましたね。生卵投げとか、いろんなことをやっていた仲間でした。
今では美術系大学進学のために私塾などに通うのは一般的だけど、その頃、鹿児島には美術の私塾というのがなかった。そこで、私が高校1年生のときに、藤浩志さんたちと県下の五つぐらいの高校の生徒が集まってそれぞれがお金を出し合い、一軒家を借りて私塾を作りました。松山先生というすごく素敵な先生がいらっしゃって、実際の契約は松山先生にお願いし、松山アトリエというアトリエを高校生みんなでつくりました。
当時はインターネットなんて無いし、誰も教えられないので、可能な限りの情報を集めて、見よう見真似で「すいどーばた美術学院」の広告とかを見て、「ああ、静物ってこうやって描くんや」とか、受験ごっこみたいなのをしていました。先に藤浩志さんが高校を卒業して、入学したのがここ、京都市立芸術大学でした。
だから、藤さんからは京都市立芸術大学の情報しか届かないんです。高校生の私もその情報を真に受け、「大学といえばもう京都市立芸術大学しかない」と全く迷うこともなく、なぜ京都市立芸術大学なのかも考えることなく、上京してきました(笑)

京都市立芸術大学のアングラ劇団 座・カルマ
日本画を選んだのは、高校1、2年生のときの担任が美術の先生で、たまたま日本画の先生だったので、顔料を使わせて絵を描かせてもらうことがあり、少し馴染みがあったことと、せっかく京都に行くなら日本画かな、くらいのつもりでした。
そうして何気なく始まった学生生活ですが、田舎から出てくる人は必ず先輩に頼ります。だから先輩も声をかけるし、後輩は先輩の人脈に巻き込まれていきます。
ちょっと話は前に戻るのですが、藤さんが所属していたダムタイプの前身となる「座・カルマ」という京都市立芸術大学のアングラ劇団が、私が高校3年生のときに鹿児島へ夏合宿をしに来るということがありました。どうせなら公演もするということで、藤さんから「お前、舞台美術やれ。」と言われ、高校生のときに舞台美術デビューを果たします。その時に、座・カルマの大学生たちから「お前は京都市立芸術大学に来るよな。で、来たらこの活動に参加するよな」と、入学前から入るクラブが決まっていたようなありさまでした。
ということで、大学の入学式直後から、藤さんがもう一つ所属していたバレー部の飲み会に連行され、座・カルマには当たり前のように登録され、という感じで大学生活が始まりました。
日本画は好きだったのですが、画壇の世界がどうも苦手だということに気づき、それ以降は年に1回程度進級のために作品を描く程度で済ませ、それ以外はすべて座・カルマとバレー部の活動に邁進しました。

日本初の国際演劇祭へ夏合宿
大学4年生か3年生の時、利賀村という富山県の山の中で国際演劇祭が開かれました。それが日本で初めての国際演劇祭で、その当時、パフォーミングアーツという言葉が生まれた瞬間でもありました。それまで演劇と呼ばれていたものの中にパフォーマンスという概念が世界で同時多発的に生まれていたんです。
座・カルマのメンバーだった私たちは、夏合宿としてキャンプをしながら、その演劇祭で作品を観ることにしました。1982年から1984年まで、第1回目から第3回目の頃です。そこで、ロバート・ウィルソンやマギー・マラン、タデウシュ・カントルなど、アーティストの先輩にあたるいろいろな人々のパフォーマンスという概念に触れ、いたく感化されました。
焚き火をしていると、ロバート・ウィルソンが隣にやって来て、「君らも頑張りなさい」と言うんです。その気になっちゃいますよね(笑)
その頃からアングラの演劇集団から、徐々にパフォーマンスという概念を帯びた創作的な表現に切り替えていきました。1984年の段階で、座・カルマという名前のままそれをやり続けるのもなと思い、先輩たちが抜けたあと、私たちの代になった時に名前を変えようということで選んだのが「ダムタイプ」。
その当時は、「ダムタイプシアター」という名前で、まだ演劇から完全には足が抜けていなかったのですが、夏休み中、学食の前のベンチで一生懸命みんなで辞書を開いて、濁音があった方がいいよなとか言いながら考えました。dumbというのは、唖(おし)という差別用語ですが、言葉が話せないという意味があったり、スラングではばかばかしい、全くアホらしいという意味を持っています。演劇から脱却したいと思っていたので、言葉が話せないというのは一つのコンセプトとして悪くないということで決まりました。
その頃なぜパフォーマンスにみんなが惹かれたかというと、演劇をとりまくシステムに馴染めなかったから。演劇って組織も作品の作り方もピラミッド構造なんです。組織の頂点に原作者がいて、次に続くのが演出家、メインの役者、周辺の役者、それを支える大道具さん、小道具さん、照明さんとか音響さん、加えて有象無象のお手伝いをしてくれる人たち。作品も同様に原作、脚本、演出ノート、、と続きます。そういう構造の中でつくることが、全然性に合わないと感じる人間が当時私が4年生だったときのメンバーに集まっていました。
だから、パフォーマンスという新しい概念の世界には、そういうのを打破する何かがあるんじゃないかと思って憧れたんだと思います。ダムタイプをつくった段階で、僕らの作品制作をするときの基本姿勢は、ピラミッドシステムではないもの、作り方をどうやったらできるかということでした。だからリーダーも演出家も決めない。出たアイデアをみんなが良いと言えば、そのアイデアを出した人が責任を取る。毎回自分が抱えるアイデアで役割が決まるような集団の作り方です。
あと、作る過程は、最初に大きなテーブルの上にみんなのいろんな興味をとりあえず並べて、それをがちゃがちゃやりながら構成し、ちょっとずつ物事を作っていく作り方をなんとか編み出しました。ものすごく時間がかかるんですけど(笑)それが、1984年から始まったダムタイプシアターの形です。

大学に残りながら続けたダムタイプの活動
それが大学4年生だったので、ダムタイプの活動を続けるために大学に残りたいと思い、もうその頃は全然日本画を描くつもりは無かったんですが、「大学にいたいから受験します」と正直に言って、日本画の学生として大学院まで行かせてもらいました。上村淳之先生が「そういうやつが1人くらいおってもいい」と言ってくださったんです。おかげでたっぷり2年間、ダムタイプの活動を続けて公演を重ねることができました。学内の公演で多少評判を呼んでいたこともあり、演劇プロデューサーが大学まで観に来て声をかけてくれることもありました。その頃はちょうどバブルが始まりかけた頃なので、いろんな企業が国際演劇祭などを開催したいとちょっとずつ動き始めた時代だったんですね。
まず声をかけていただいたのは、アートスペース無門館でした。そこの遠藤寿美子さんという、すごく愛のあるおばちゃんがダムタイプのことをものすごく気に入ってくれて、ありえないくらいえこひいきしてくれました(笑)無料で貸してもらったり、通常では考えられないくらい長い期間、稽古場として使わせていただいたり。初めて学外で表現する機会をいただいたのもアートスペース無門館。それから、そこで発表するようになっていきました。
こぼれ話ですが、ダムタイプの活動が軌道に乗ってきて、私は大学院を中退することになります。軒並み他のメンバーも全員中退(笑)時代の影響もありますが、中退が称号のようでかっこいいと思っていました。実はみんな立派なアーティスト、活動家になっているんですが学歴はボロボロ。今考えると、先生たちにめちゃくちゃ面倒くさいことをさせてしまったなと思います(笑)

海外ツアーを経て、ダムタイプ一時解散
その後、1986年の大阪国際演劇祭で国際デビューを果たします。国際と付いているだけあって、海外のプロデューサーも観に来ていて、声をかけてもらったり繋がりが生まれました。資金調達も兼ねて東京で公演をする必要があり、ワコールアートセンターによる「スパイラル」のプロデューサーが注目してくださっていたおかげで何度か公演をさせていただきました。そして東京デビューを果たし、1988年頃には海外ツアーが始まります。ただ、ツアーはものすごく評価が高かったんですが、かなりの借金を抱えて帰ってくることになりました(笑)
最大のミスは、当時のアメリカはスーツケースを2個まで機内持ち込み可能だったのでニューヨーク公演はそれで問題なかったのですが、そこからヨーロッパへ移動するときは1個しか持ち込めなかったことです。メンバーそれぞれの半分の荷物(しかも35キロみっちりで重量オーバー)を預けるために超過料金が膨れ上がっていきました。初めての海外公演だったのでプロフェッショナルでもなく、ドタバタでした。
その借金を抱えたままでは生きていけないので、帰国後は一時解散となり、それぞれ夜の仕事に行ったり、就職したり。でもメンバーの古橋悌二、穂積幸弘、泊博雅くんと私の4人だけがとどまり、私は大道具のアルバイトで借金を返しながら、出町柳にある清和テナントハウスという元倉庫のダムタイプオフィスを維持していました。同時に、次の作品のファンディングをするため、ワコールアートセンターやセゾン文化財団と話し始め、なんとか資金繰りが見えてきたところで作品プランのベースをつくり上げました。それが『pH』。軌道に乗りそうだったので、就職したやつも辞めさせて、無理やり呼び戻しました(笑)
そして再び東京公演、海外ツアーを行います。その頃になると、最初の大阪国際演劇祭で出会った海外のアーティストたちが若手のフェスティバルディレクターに抜擢されていたりするので、彼らがどんどん私たちに声をかけて呼んでくれたんです。『pH』は毎年いろいろな所に呼ばれ、各地を駆け巡っていました。その頃は1年の半分くらい海外にいたので、稼ぐための仕事ができず、家賃も払えなくなりました。ダムタイプとしては国際的にもめちゃくちゃ評価してもらえましたが、パフォーマンスはもともと収支が合わない世界なので。そこで税金に追われることを逃れるため、ダムタイプのオフィスに住んではいたけれど、転出届をして転入届をしないことで意図的に住所不定者になりました。10年パスポートを取得して、それだけがアイデンティティーという状態でした(笑)
招聘先から制作費をいただいていましたが、全部作品に突っ込むのでギャラは無いに等しい。ダムタイプはワークインプログレスで作品を発表していて、ちょうどベルリンの壁が崩壊したり、湾岸戦争が起こっているときだったので、作品を変えながら海外をまわりました。
海外にいる間はアパートが提供されるなど、生活は保障されていたのですが、帰国するとほんまにすっからかんなので私は大道具の仕事をガンガンやっていました。そのお金でまた海外へ行くというサイクルです(笑)

エイズにまつわる問題が生活や制作の基本形に
京都芸術センター開設前のアートフェスティバルの一環で、1991年、京都市美術館の大陳列室でダムタイプが『pH』を上演することになり、中退して縁が途絶えていた大学の後輩たちがたくさん手伝ってくれて、後輩たちとの関係が急激にスタートしました。ダムタイプのオフィスにもよく出入りしてくれるようになり、その中に石橋義正くんなどキュピキュピのメンバーもいて、うちの編集システムを使って、彼らの映像を作り始めたり。後輩や周辺の人たちがいたから、京都での活動は本当にしやすかったと思います。
こうした人間関係の土台ができていた頃、1992年に古橋悌二からHIVに感染していることを告白されました。それからは、エイズにまつわる問題が一挙に自分たちの生活や制作の基本形に入ってくるようになる。後輩たちもそうした活動にがっと参加してくれるようになり、コミュニティセンターのようにいろんな活動をしている人がオフィスを出入りするようになりました。手狭になったので、新たな拠点となる場所を探していると、演劇評論家の方のお知り合いが、空き家になっているので文化的なことに使うなら地代だけでいいよと物件を貸してくださることになりました。京都大学のすぐ東側、吉田山の麓にある、2階建ての日本家屋。庭付きのいい空間でした。
そこでArt-Scapeというインディペンデントのアートセンターみたいなものを始めて、エイズやジェンダー、セクシャリティを考えたり活動したりする拠点になっていきます。いろんな運動が活発に起こり、すごく良かったけれど、そこの空間が活発になればなるほど一般の人が来にくくなってしまいました。どうしても何かを突き詰めていたり、プロフェッショナルな世界というのはそういう無言の圧力のような、敷居を高く感じさせる空間性を帯びることが多い。
「ここもほんとは誰でも来れる空間としてつくったのに、そうなっちゃったな」と思って次に編み出したのが、オールナイトの自主運営のバー、ウィークエンドカフェです。Art-Scapeの活動にも参加してくれていた、佐藤知久くんがまだ京大の学生だった時で、京大の西側にある地塩寮の寮生と話をしてくれて、1階のデッドスペースを片付ける代わりに使わせてもらえることになりました。向かいの酒屋さんから仕入れて、原価切り上げで安くみんなで飲める、ホームパーティーの延長のように営業していました。
その頃は携帯も無いし、非営利の活動なので広告も打っていなかったけれど、口コミだけであっという間に300人が集まりました。最初はエイズのいろんな活動をされている方が口コミでいろんな人を連れてくる場所でした。京大生も大学のすぐ横でやっているから、嗅ぎつけてどんどん入ってきました。物理とか、宇宙理論をやっている学生が来たりして。よく考えるとスノッブだけど、そういう人々が集まる京都では、本当にエポックな空間になって、3年間やることになりました。
その間、ダムタイプは『S/N』というプロジェクトを国内外で発表していました。でも、私自身は、ウィークエンドカフェの空間のあり方にぐっと来ていて、パフォーマンスでの表現より、こういう場作りとかの方がビンビンにくるような感覚をちょうどその頃からもつようになっていて。『S/N』をやっている最中に古橋悌二が亡くなるのですが、それを機に、より一層、もうパフォーマンスはええか、となりました。
一つの方法で世の中を変えるというのは、ちょっと無理があるよなと。アートで社会に影響を与えられることも実感していたし、Art-Scapeの活動も充実していたけれど、それよりはウィークエンドカフェのように人がフラットに集まっていろんな意見交換をし続ける、そういう場をいろんな形でつくる、社会実装していくのを、自分の仕事にした方がええんちゃうかなと思って。
私自身はもうダムタイプを辞めることにして、そういう場作りの活動にシフトしていきます。

奇跡的な空間
ウィークエンドカフェは、本当に奇跡的な空間で。しつらえも運営もとてもシンプルでした。テーブルに布をかけて、カウンターを作るだけ。そこにビールとかワインが並ぶ。パーティーに行って知り合いがいないと、壁際に立ってどう振る舞えばいいのか戸惑うことがありますよね。でもここでは、その場にいるみんなが運営者みたいな空気があって、目の前で誰かが飲み物をこぼしてくれて、仕事が発生する方が、その場に居やすいということが起こります。だから、気が付いたらみんなカウンターの内側にいて、雇われマスター経験者ばかりになっていく(笑)200人ぐらいお客さんが来たとしてもみんな経験者なので、それぞれが「俺の店」、「俺の空間」と思って、準備から片付けまでとてもスムーズ。海外からのゲストをそこに呼ぶとすぐに、じゃあレクチャーをやろうとなります。憧れの、ワインボトルをカンカン鳴らして「今から始めるで」と注目を集めることもできました。
けれど、3年目に関わってくれていた寮生たちの卒業や生活の変化があったこと、その場所が歴史的建造物に指定されて改修工事に入るなどの理由で地塩寮は使えなくなりました。それでこの企画は終わってしまうのですが、終わったら困るのは、集まってくれていた人たち。そこに集まりさえすればみんなに会えたので、連絡先の交換なんてしていないし、あだ名で呼び合っているから本名も分からない。例えば特に困っていたのは看護師さんたちでした。エイズなどケアに携わっている方々は、非常に過酷な労働をしていて、しかも仲間は増えない、社会はなかなか変わらない、患者は増える一方。だからストレス発散が必要だったのだろうと思います。ウィークエンドカフェに来れば、ある程度考えてきた人や勉強している人がいるので話が分かる、話も聞いてくれる、ひょっとしたら人材も見つかる、というのですごく便利だったらしいです。
それで次の場所を探してくれて、できたのが、バザールカフェ。同志社大学の近くにある古い洋館で、そこの宣教師館を使えないかと交渉してくれたようです。女性の活動や社会的な活動をするのであれば無料でいいと言っていただき、1階部分を使わせていただくことになりました。

自分たちがつくった空間は自分たちの生活を豊かにしてくれる
バザールカフェの後は、改装を気に入った素人集団でID10(アイディー・テン)という改装、施工をするグループをつくりました。手がけたお店がどんどん増えていくと、自分たちにとってすごく行きやすいんです。吉田屋料理店とか、一時期みんなが通ってた文化的な人々が集まりやすい飲み屋ができたりとか、みんなが使える新しい形のお店ができていくのが面白かった。1995年の阪神淡路大震災では屋台をつくって行ったり、ボランティアでみんながいろいろと関わったりしました。
その当時、自分たちがつくった空間は自分たちの生活を豊かにしてくれるとは思っていたけれど、この活動をアートだとは思っていませんでした。けれど、続けているとこの活動を表現として見てくれる評論家やキュレーターが少しずつ現れてきました。私はダムタイプを辞めてから大工として生きてきたのですが、再び美術館などの企画に呼ばれるようになります。
震災以降、いろんな形で社会と表現の関わりが問われるような時代がやっとスタートしました。その頃はまだソーシャルアートの概念はなかったけれど、場作りやセルフビルドという概念が少しずつ生まれつつあり、自分の中で美術に戻っていく感覚が起こりました。相変わらず食えないんですけどね(笑)
2000年初頭には、「そういう表現をする人」としての認知度がちょっと高まっていました。自分でも自分の活動をなんと言っていいのかはまだ分かっていなかったのですが、学生時代にヨーゼフ・ボイスが社会彫刻という言葉を残してくれて、そこにヒントがあるのではと思い活動を進めていきます。言葉自体は、もっと複雑で重い言葉ですが、社会彫刻という概念には今までのメインストリームの作品、美術作品のつくり方やあり方とは違う形の、芸術と社会との関係をつくれそうな予感がありました。

これまでの活動を言語化、理論化していく 二方向への転機
そんな中、大学の関係者から「大学(で働くの)チャレンジしてみいひん?」と声をかけてもらいました。しかも彫刻。日本画専攻出身で彫刻なんて一度も学んだことはないのですが。ダメもとで応募してみたら受かって、人生で初めて給料をもらう立場になりました(笑)ちなみに、住所不定者から社会復帰したのは1999年頃、40歳手前の頃です。虫歯になって、どうしても痛みに耐えられないのに健康保険証も無いということで、区役所に相談へ行きました。そこで職員のおばちゃんに「最低限のやつ作るから」とめっちゃ怒られながら作ってもらいました。そして、病院に行ったら必ず帰っておいでと。住所を決めることから始まり白色申告をするなど、社会復帰の手伝いをしてくれました。これぞ社会のセーフティーネットだと感心しましたね。おかげで大学職員にもすんなり(笑)
それ以降は学生たちと一緒に社会と関わりのある表現はどういうものなのかといったことを考えながら、自分なりに理論を組み立てたりしています。教職に就いたことは大きな転機でしたね。
一つは自分の中では曖昧で、でも直感で選んできたものを抱えた状態で、今度は教える立場になるので、一生懸命客体化、言語化することになる。これまでの活動の価値を考える段階にいかせてもらったと感じています。それを考えることで今度は、自分の次の動き方を考えるようにもなりました。
同時に、安定した収入の裏付けによって家族をもつことができました。大学で働きだす1年前から今のパートナーと共同生活を始めたのですが、相手に連れ子がいたので、ある日突然私は父親になりました。でもその時は経済力が伴っていなくて、非常に苦労しました。だから、給料をもらう立場になり初めて少し安定することができ、未来を計画することができるようになって視野が広がりました。
それまでは、人が真似できないくらいソリッドな生活をして、1人で生きてもええかと思っていたんです。大学に入っていなければ、たぶんまだソリッドな生活を続けていて、もしかしたらもう生きていないかもしれない。生き延びていたとしても、活動は続けていただろうとは思うけれど、表現とも思っていなかっただろうし幅が狭いままだったと思います。でも、他者と生活を始めて、家族を増やしていく方向に切り替わったことと、「家族はどのように拡大家族として広がっていくのか」という問いや、自分が抱えている表現の進むべき方向が微妙に重なってくるようでもありました。

教育を担っている
最近大きな変化として感じているのは、自分が教育を担っているということが、いろんなことを考えるときのベースにあるということです。ここは大学ですが、個人的には幼稚園、小中高なども含めて幅広く子どもたちの教育に対して目を向けています。
私の子どもがコロナ以降不登校になって、今は自然学校のようなフリースクールに通っています。毎日自転車で山の中まで。のびのびしていて、ワイルドで、すごくたくましくなりつつあります。これ、悪くないよなと思っていて。競争原理からは外れてしまうけれど、違う競争力を身に付けているのではと思ったりします。幼児教育の仕事を依頼されることもあり、その構想を練るときは、もう私の頭の中には通常の美術教育はありません。そうではない形のものをどうつくれるだろうかと考えています。環境や家族の形などさまざまなことが影響するので大変ですが、学長という立場だからこそ向き合っていかなければと思いますし、これからいろいろと試してみようと思っています。
プロフィール
1961年鹿児島生まれ。京都市立芸術大学に在学中に友人達とパフォーマンスグループ「ダムタイプ」を結成。国内外で活動。1990年代頭にメンバーのHIV感染を機に、AIDSを取り巻く問題に対しての活動を始め、ダムタイプを離れた後、「共有空間の獲得」をテーマに人々が出会い交流する場の創造を活動とする。2010年から京都市立芸術大学の彫刻専攻の教員。2025年4月より同大学の理事長・学長に就任。