裸足で踊ったあの日から

小倉笑|京都在住歴 11年
29歳にして、すでに11年の京都在住歴がある小倉さん。コンテンポラリーダンスに出会った中学生の頃の記憶、京都に通った高校生の頃の記憶、どれも瑞々しく語っていただきました。大学に進学しない人生を選択し、京都でアーティストとして生きる暮らしに迫ります。
取材場所は、10年以上続けているというアルバイト先の「うたかた」。
取材:2025年1月
ダンスとの出会い
岐阜県の大垣市出身で、4人兄妹の末っ子です。16歳の頃から「絵描き」と名乗る父と、主婦の母のもとに生まれました。父は反骨精神が強く、例えば、「芸術大学に行けば芸術家になれる」といった型にはまった考えが嫌いで、その影響を強く受けて育ったと思います。その父が家でレコードを爆音でかけていて、ジャンルは雑多だったのですが、オペラも含まれていたからか、オペラみたいな歌い方をする子どもでした。3歳ぐらいからヤマハピアノ教室でピアノを習っていて、歌のレッスンもあったり、音楽にずっと触れていました。その時から歌うことが好きでしたね。
ダンスに出会ったのは、小学五年生のときに参加した市民公募型のミュージカルです。学校でプリントが配られ、「歌が歌えるんだ、うわ、これ参加したい!」と応募しました。ほかの子よりもちょっと歌がうまかったみたいで、役をつけてもらえたのですが、ダンスができなさすぎて1ヶ月で降ろされてしまいました。そこで初めてダンスをしたので、「ダンスって難しい、これくらいの時間で振付を覚えられなければ役を降ろされるんだ」と思った記憶があります。それからダンスにすごく苦手意識を持つようになりました。
一方で、その事業を統括していた児童劇団では、声楽技法のようなものを教わることができました。方法論に則って歌わなければいけないことに当時は疑問を抱きましたが、今となっては調音や音を聞いてリズムを書き出す訓練は良い時間だったと思っています。

バレエシューズを脱いでいなかったら
そんな中、中学二年生のときに、岐阜県の可児市文化創造センターと大垣市文化事業団の合同で『オーケストラで踊ろう!』という大きな規模の市民公募型事業が行われることになりました。ただ、大垣市の応募が少なかったため、私が続けていた児童劇団員全員が強制的に参加させられました。当時は、「コンテンポラリーダンスなんて全然知らないけど、どんな感じかな」と思っていましたね。それがコンテンポラリーダンスとの出会いです。その振付に来ていたのが、ダンスカンパニーのMonochrome Circusです。坂本公成さん、森裕子さん、当時のメンバーだった野村香子さん、合田有紀さん、荻野ちよさんなどが教えに来てくれました。
それまでは、バレエシューズを履いてミュージカルに必要なジャズダンスをやっていたのですが、レッスンで「裸足になりましょう」と言われて驚きました。裸足で踊るの?と。動きの指導では、「空気の玉を持っていると想像して、それを大きく動かすように」などと言われて。それまでは肩から綺麗に腕が伸びるように、といったことを意識した練習しかしたことがなかったので、カルトっぽいな、やばいなと思いましたね(笑)イメージを掴んで身体を動かすなんてことは初めての体験で「うわあ、こんな動かし方もあるのか」と興奮する一方で、正直なところ、少し抵抗を感じていました。
半年間、毎週30〜40人ほどが集まって稽古していたのですが、同世代のティーンエイジャーは恥ずかしがってやりたくないと言い出す人がいて、それにつられる人も結構いました。でも私はその間で心が動いていって、「あれ、裸足で踊るのも、おもしろいかもしれない」と思い始めました。何かきっかけがあったわけではないのですが、抵抗するのは損だな、楽しまないのも変だなと思って。そう気づいてからはどんどん楽しくなりました。それから大垣市の担当で来ていた森裕子さんや荻野ちよさんとも仲良くなれました。
あの時、私もバレエシューズを脱いでいなかったら、今ほど楽しく踊っていないかもしれません。京都に出てこようなんて思っていなかったかもしれない。そこで心が開けたから、本番もすごく楽しかった。

ちょっと背伸びをして飛び込んだ、京都でのダンスワークショップ
それから、Monochrome Circusの人たちと、もっと関わってみたいと思うようになりました。すると、ゴールデンウィークに京都国際ダンスワークショップフェスティバル(通称:京都の暑い夏)というのがあると教えてもらいました。中学三年生の時に初めて参加し、翌年も参加。その時初めて、その後何度もお世話になる京都芸術センターに初めて足を踏み入れました。
「暑い夏」は、海外からもたくさんの先生が来ます。でも私は英語が話せない。その中で日本人が先生のクラスなら受けられるだろうと思って、高校一年生のときに唯一申し込んだのが、舞踏のレジェンドである室伏鴻さんのクラスでした。当時、舞踏なんて知らなかったのですが(笑)
その時のことは今でも鮮明に覚えています。場所は京都芸術センターの制作室7でした。「東北の畑の横でくるまれた胎児が…」などの室伏さんのリーディングに合わせて、「ケーーーーーッ!!」と奇声を発しながらポージングする。何が何だか分かりませんでしたが、ほかの参加者もやっていたので、この場はこういうことをする場所なんだ、自分もやるしかないと意を決して「ケーーーーーッ!」とやりました。おもしろかったです。
地元の周りの子たちは誰も参加していなかったので、ちょっと背伸びをして大人になった感じがして嬉しかったです。飛び込んで良かったと思います。その後も欠かさず毎年、暑い夏に参加しました。高校生になってからはアルバイトを始めてお金を貯め、貯めていたお年玉を使って毎週のように京都へ通い、公演を観たり、ワークショップに参加しました。京都でアルバイトをしていたこともあります。金曜日、授業が終わってから夜に京都に着いて、土日の朝は京都でバイトをする、今ではやりたくないですがタフでした(笑)
ヴィラ九条山に滞在しているアーティストの作品に参加することもありました。京都で活動すると様々な国籍のアーティストと関われる可能性があるということも、この頃に知りました。

高校に行く時間がもったいない
母からは、高校は卒業しなさいと言われていたので、毎朝輸送されるように学校へ通いました。農業高校に通っていたので、とりあえず牛を育てて単位を取りました。先生からは「で、小倉は何になりたいんや?」と聞かれたり。高校に行くのは時間がもったいないと感じていたし、辞めたいという気持ちもありました。今は卒業しておいて良かったとは思うのですが。
そんな高校生活の最後の年、Monochrome Circusが『Lemming』という群舞の作品の出演者を公募することになりました。公募だったので応募して、めでたく参加できることになり、神戸と福岡の2公演分、リハーサルや本番の日は全部高校を休みました。そのうち、『Lemming』がウィーンのフェスティバルに招聘されることが決まりました。もちろん私は行きたいと言いましたが、裕子さんが「あかん、高校生やから」と。でも公成さんが「別にいいんちゃう」と言い出して。最終的に行けることになりました。高校の先生に話したら、農業高校なので「なんや、それ」となって、校長先生の許可を取ったり、フェスティバルからも招聘状を発行してもらったりとバタバタしましたが無事に行くことができました。それが初めての海外です。

作品を作る過程がおもしろい、そこにいる人たちと一緒にいたい
高校卒業後、京都へ移住しました。大学進学を検討したこともありますが、昔から父に「大学に行くなら自分で稼いだお金で行くか、奨学金を借りるかして行け」と言われていました。本当に行きたいのか考えろ、と。京都精華大学が気になっていましたが、学費が高すぎて諦めました。それに、私が大学に行かなくても、大学で勉強した人が仲間にいるから、その人たちから学べばいい。私は現場で学ぶ方を選択しました。
中学三年生の時に初めて暑い夏に参加したときから、どんどん京都の友だちや知り合いが増えていって、そういう繋がりがあったから京都への移住は自然と思い描いていたのだと思います。どこに住めそうか、どんなことができそうか想像することができました。高校生の時からお世話になっていたのは京都芸術センターの情報コーナーです。全国から公演、展覧会やワークショップ、オーディションのチラシが届いて並べられています。世間がiPhoneやスマートフォンを持ち始めたくらいの時期で、インターネットに情報が集約されているような時代でもなかったので、紙の情報が集まっていて重宝しました。そこで得たオーディションの情報を活かしていろいろな作品に携わり、たくさんのアーティストと出会うことができました。
作品に出られることも楽しかったですが、作品を作る過程がおもしろかったし、そこにいる人たちはおもしろい人ばかりで刺激を受けていました。高校の友だちは誰が付き合ったとか、あの芸能人はどうだとかの話をしていて、話が合いませんでした。作品を作る現場で出会うダンサーたちは、自分はどう生きたいのかといったことを話していて、それが楽しかった。そういう人たちともっと一緒にいたいと思うようになりました。結局、高校は自分から望んで行った場所ではなかったというのが決定的な違いだと思います。

うたかたの女将さん
京都に来てからはアルバイトをしながら、せっせとワークショップに参加したりオーディションを受けました。周りの10歳年上の人たちも、アルバイトをしながら芸術活動をしていたので自然な生き方でしたね。飲食店や小売業などを転々としましたが、稽古や本番などでシフト上の問題があったりうまくいかなくて仕事先が定着しませんでした。
そんな折、船岡温泉で出会ったのが、今日の取材場所にもなっているおばんざい屋「うたかた」の女将さんです。浴場内で最初に女将さんを見たときは、極道の妻かと思ったのですが、女将さんから「お姉さん、何してはるん?」と話しかけられて。ダンスをしていると返すと、バイトは?と聞かれ、「やってるけど、あまりシフトに入れないんですよ」と言うと、「ほな、うち来るか」と言われました。でもその時は、ヤクザの事務所に連れていかれるのかと思っていたのですが(笑)
電話番号を教えてもらって、なんか食べにおいでと言われました。お金がないと言うと、「そんなん、お金なんていらへん」と言われて。半信半疑でお店に行ってみると、カウンターには茶杓職人の方や北区でお菓子屋さんをしている女将さんなどの常連さんがいました。ひとしきり食べたあと、「こんな感じのお店やけど、どう?」と聞かれ、その場で「働きます」と答え、もう10年以上になります。女将さんからは仕事だけでなく、大人としての基本的な立ち振る舞いに始まり、常連さんからご厚意でいただくお土産に対してのお礼や、お誘いいただくホームパーティー、さまざまな行事での振る舞い方。京都の文化の中でどう人と関わるのかを教えてもらいました。

女将さんは、以前は料亭で雇われ女将をされていたのですが、20年ほど前に独立して、「うたかた」を経営されています。私と同じように女将さんからいろんな教育を受けた歴代のバイトさんたちは、大学卒業とともにさまざまな場所へ巣立っていきました。私が船岡温泉で声をかけられたときも、隣に「うたかた」のバイトさんがいたんです。その日は女将さんと店(うたかた)に泊まったそうで、翌朝、女将さんに着付けをしてもらって卒業式に行かれました。「うたかた」はそういう場所です。今では私が新しいバイトさんに指導をするようにもなりました。
お客さんは大事、やっぱり心地よくいてほしい。公演をする時も、良い時間を過ごしたなと思ってほしいです。細かいことが気になるようになったのは、ここで働いているせいかもしれません(笑)
「うたかた」は、特別な時間を提供する場所だから、どういう言葉遣いで、どんな態度、空気感で、どういうものを提供するかというのを、ちゃんと考えないといけないと教えてもらいました。それは舞台を作るときにもすごく繋がっていることだと思います。

Monochrome Circusのアンダースタディー
京都に出てきたときの話に戻りますが、その年に、Monochrome Circusの若手登竜門のような作品『HUSAÏS』を踊るための、アンダースタディーオーディションというものがありました。無事に受かり、一緒に公演もできたので、Monochrome Circusに少し認めてもらえたように思いました。高校生の時から、「ダンスは「暑い夏」のように楽しいことばかりじゃない、アングラだよ、お金も稼げない。だからダンサーにはならない方がいい」などと言われていましたが、その時はドキドキ、ワクワク、楽しみな気持ちと不安な気持ちの両方がありました。少し前のMonochrome Circusは、専属ダンサーが所属するスタイルのカンパニーだったので、私もそうなるのかなと少し期待していたところもあります。専属ってカッコイイじゃないですか(笑)
でも、「あなたには放任主義でいく、どこでも、なんでもやっていい」と言われて、当時は、えっという気持ちでした。けれど、Monochrome Circusの公成さんや裕子さんは、私が歌も歌うことを理解して、そう言ってくれたのだと思います。最終的には素直に受け止め、結果的に、Monochrome Circus以外のいろいろな作品に出演させてもらうようになっていきました。

康本雅子さんとの出会い
そんなある日、ダンサー・振付家の康本雅子さんから急に、「今度作品を作るので、一緒にやってくれませんか」と連絡が来ました。面識はあったけれど、まだ何者なのかほぼ知らない関係性の頃です。にも関わらず、「仕事だ!」と思って、二つ返事で引き受けました。
というのも、私は実際に会って、自分の目で確かめてみるまでは、誰かのことを周囲の評価などで決めつけたりしないようにしています。康本さんに対して周りの人がちょっとざわざわしているのを感じてはいましたが、特にインターネットで調べることはしませんでした。けれど、クリエーション中に「今度、大きい舞台の振付をしているからよかったら!」と誘っていただいて観たのが、名古屋で上演された松尾スズキさん演出の舞台だったのです。康本さんが本当に振付をして、本当に舞台で踊っているのを見て、「あれ、この人はもしかしたらなんかものすごい人かも」と、ようやく気づきました(笑)そう思った理由にネームバリューもありますが、踊っている姿に説得させられたというか。
そして、その時に作っていたのが2017年に京都で初演、2018年に横浜で上演した『子ら子ら』です。これが初めて関東で舞台に立った作品になりました。その後、康本さんと踊ったということが、いろんな人に存在を知ってもらえるきっかけとなり、ほかの作品への出演なども増えていきました。

ダンサーや振付家としてはもちろんですが、康本さんの人格からも学ぶことがとても多いです。すごく変で面白い人ですが、やりたいこととやりたくないことをしっかりと口にできて、自分の指標で良いと感じたものには「良い」という眼差しを向けることができる人です。誰かを自分の作品のダンサーに起用した際、観客からの「あの人の踊りよかった。いい演者だった」という言葉に本気で喜んでいる姿を見て、すごい人だと思いました。自分の審美眼に自信を持っていて、怖気づくことなくそれを他者に開くことができる。康本さんがこれだけ活躍されている理由の一つがここにあると感じました。
あと、横浜で上演した際に、康本さんが私のことを「京都から妖怪連れてきたから!」と紹介したことがありました。その時まで、私は自分が妖怪であると自認していなかったのですが、康本さんはうれしそうに、自慢げにそう紹介していたので、なんだか腑に落ちてしまいました。
それまで、暗黙の了解としてダンサーに求められている「コンテンポラリーダンサーっぽさ」や「綺麗さ」みたいなものに対して、自分はそうなれないと感じていて。身長も低いし、見た目もそぐわない気がして難しさを感じていた時に、妖怪という新たな要素を提示され、「それでいいんだ」と思いました。しかも、「妖怪が来たんだね」とその場にいた人たちにもすんなり受け入れられ、妖怪として自信を持つことができたのです。いろいろな面で、康本さんとの出会いはすごく大事だったと思います。

出会いの連続の中で
けれど、コロナ禍で人と出会うこと、話すことが難しくなりました。コロナ禍が始まった2年後には、ロシアのウクライナ侵攻も始まり、何が正しいか分からない中で、どの立場や視点で意見を持てばいいのか分からない状態になり、そのことがなんだか気持ち悪いと感じていました。侵攻が始まって間もなく、ウクライナの劇場が破壊されましたよね。そのニュースを見て、戦争が終わって、復興が始まったとしても、おそらく芸術を発信する場所の復興は最後の最後の最後になってしまうのかもしれない、などと想像して怒りのようなものを覚えるほど、ショッキングでした。自分にとって劇場とはどういう場所か、人が劇場とする場所はどういう所なのか、といったことを友人たちと話しました。それらを私なりに消化/昇華するために始めたのがKYOTO Cultural Festivalです。3年間続けていますが、中核にあるのは今でも、劇場とはどういう場所なのかという問いです。

少し話は変わりますが、企画って「できるかも」と思わないとできないじゃないですか。自分の企画としてKYOTO Cultural Festivalを始められたのは、友人のNishi Junnosukeくんに鍛えられたからだと思います。Junnosukeくんから突然電話で一緒に企画をやりたいと言われ、また二つ返事で引き受けてしまったことが始まりです。軽いイベントを1回組むくらいのものだと思っていたのですが、ふたを開けると、月に2回コロナ下のUrBANGUILDを借りて仲間同士で実験できる場所をつくるという企画「Super practice」(通称:Spra)を約一年間継続するということでした。しかも、彼はちゃんと質を保った企画にするという縛りを課していたので、生半可な気持ちでは到底こなせませんでした。
以前は、企画することは、かなりハードルの高いことだと考えていましたが、さすがに毎月2回、企画の準備と実施を繰り返していると、企画に必要なことがだんだんと分かってきました。「企画って、できるものなんだ」という現実味を感じられるようになりましたね。あのとき彼に声をかけてもらわなければ、今でも私は公演やイベントのやり方が分からないままだったと思います。
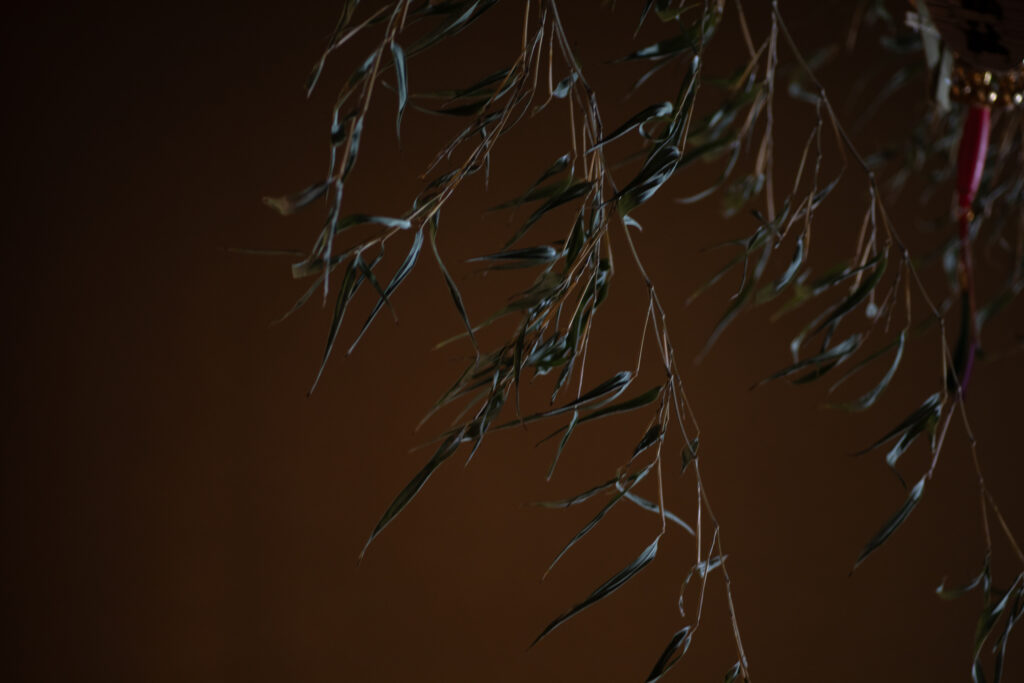
これからやりたいこと
2023年から京都市東山青少年活動センターで中学生から30歳までの方を対象としたダンス講座のナビゲーターをさせていただいています。約3ヶ月半かけて、10〜15名ぐらいの参加者と一つのダンス作品を創り、成果発表の公演まで行うものです。多様なバックグラウンドの人と対話形式でクリエーションを進めるのですが、一人ひとりが普段感じる喜びや抱えている悩み、生きづらさに注目しています。そこからダンスの立ち上げを試みる中で、身体の状態や、人の行動に影響を及ぼしているものが何なのかが気になるようになりました。動物的本能、育った環境などいろいろなものが影響していますよね。例えば「京都に住んでいる人」という括りで見ると何かの傾向が見えてくるかもしれません。
身体の状態を注視するようになってからは、作家として振付や演出、イベントをする時に大事になるのは、「出演する人や関わる人が最もその人らしさを発揮できるしつらえを考えること」だと思うようになりました。この意識や関心が、今後、どのような作品づくりや活動の出発点になっていくのか、楽しみにしていてください。
プロフィール
1996年岐阜県大垣市出身。10歳から声楽とダンスを始める。2014年より京都を拠点に活動。以降、Monochrome Circus、康本雅子、笠井叡、mama!milk等の舞台やコンサートに出演。自身でも作品創作を行っており、2021年に創作団体SMILEを立ち上げ、「SMILE」「A human dodging a fried oyster / 牡蠣フライを避ける人間」「SUPER COMPLEX」などの舞台作品を発表。ヨコハマダンスコレクション2022コンペティションⅠにて奨励賞を受賞。
セゾン文化財団 国際プロジェクト支援(2023-2025)、International Coproduction Fund of the Goethe-Institut.(2025)の助成を受け、Belle Santos(独)と共同で作品創作を行い「MORNING TIME / 朝の時間」を発表するなど国内外で活動。2022年よりKYOTO Cultural Festivalを主催。2025年度より京都国際ダンスワークショップフェスティバルの共同プログラムディレクターに就任。ダンス、音楽、舞台作品創作、親子・青少年向けWS、イベント企画など、様々なジャンルを横断しながら活動を行なっている。